2025年7月31日(木)発刊!
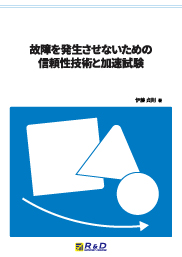
本文サンプルはこちらからご確認いただけます
はじめに
第1章 故障を発生させないための信頼性技術の考え方
1 信頼性工学と信頼性保証
~使う立場と作る立場の信頼性~
2 バスタブカーブと故障率
2.1 バスタブカーブと故障の種類
2.2 品質の要求レベルのアップと故障率評価の課題
3 信頼性は常に脅かされている
3.1 製品の軽薄短小化密閉化への課題
3.2 商品を取り巻く環境の変化への課題
3.3 課題を解決するためには
4 キーとなる故障メカニズム
4.1 故障メカニズムと故障の芽
4.2 故障/故障モード/故障メカニズム
4.3 故障メカニズムの分類と対応
4.4 故障メカニズムの各分野共通性
4.5 信頼性解析は故障メカニズムを知らないとできない
4.6 故障メカニズムは難しいか
4.7 故障メカニズムが信頼性保証活動の中心
4.8 開発/設変/新規部品採用は故障メカニズムとの戦い
5 信頼性保証加速試験と故障の芽解析の進め方
第2章 故障メカニズム
1 熱ストレス
1.1 拘束応力
1.2 拡散、変態、軟化
1.3 状態変化(融解、蒸発、沸騰、凝縮、凝固)
2 湿気ストレス
2.1 水の三体
2.2 空気中の水分量
2.3 結露
2.4 水の極性と吸湿/透湿
2.5 水溶性
3 応力ストレス
3.1 不均一応力 応力集中
3.2 持続的応力
3.3 繰り返し応力
3.4 クリープと疲労の組み合わせ
3.5 微摺動摩耗
4 ガスストレス
4.1 製品の外部環境と内部環境
4.2 樹脂とガス
4.3 高分子の加水分解
4.3.1 高温で起こる加水分解
4.3.2 常温で発生する加水分解
4.4 環境応力割れ
4.5 ブリード性
4.6 腐食
4.6.1 (電気)化学腐食──酸化剤による腐食
4.6.2 異種金属接触腐食(ガルバニック腐食)
4.6.3 濃淡電池
4.6.4 選択腐食
4.6.5 孔食
4.7 応力腐食割れ(応力ストレスとガスストレスの組み合わせ。
SCC:Stress Corrsion Cracking)
4.8 水素脆性(応力ストレスとガスストレスの組み合わせ。
HE:Hydrogen Embrittlement)
4.9 銀(Ag)と硫化
5 電気ストレス
5.1 ジュール熱
5.2 耐圧劣化
5.3 絶縁劣化
5.3.1 電解腐食
5.3.2 陰極腐食
5.4 電界拡散
6 エレクトロケミカルマイグレーションの伸長メカニズムと対策
(Electro-Chemical Migration:ECM)
6.1 はじめに
6.2 Ag、Cu、SnのECM例
6.3 ー極からの伸長、+極からの伸長の基本原理
6.4 金属イオンの溶出に必要な水分とペア
6.5 ECMの伸長形態の電流による変化
6.6 ペースト溶剤中で発生する高温ECM
7 ウィスカ(Whisker)の伸長メカニズムと対策
7.1 はじめに
7.2 ウィスカはなぜSnとZnだけか
7.3 ウィスカを理解するためのSnの特性
7.4 Snウィスカの各種伸長メカニズム
7.4.1 粒界に下地金属浸入によるウィスカ
7.4.2 腐食(酸化)によるウィスカ
7.4.3 温度サイクルウィスカ(空気中、窒素中、真空中)
7.4.4 押圧によるウィスカ
7.4.5 Inによるウィスカ伸長メカニズム
7.5 亜鉛めっきウィスカ
7.5.1 亜鉛めっきはめっき時に圧縮応力が発生する
7.5.2 ウィスカ発生の温度依存性
7.5.3 めっき時の圧縮応力原因と対策
8 無機りん(赤りん)系難燃剤による故障メカニズム
8.1 はじめに
8.2 赤りんによる難燃剤とは
8.3 赤りん難燃剤による故障事例
8.4 発生する故障メカニズムの基
8.5 成形と無機りん系難燃剤の粒
8.6 絶縁劣化から起きる故障メカニズム
8.7 ホスフィンガスから起きる故障メカニズム
第3章 信頼性保証加速試験
1 試験を加速させる考え方
1.1 部品材料の寿命判定には機能寿命と特性寿命がある
1.2 試験を実施する前に
1.3 早く結果を出すことと加速試験
1.4 加速させ方の基本の5つ
1.5 加速試験で通常使用時を推定するときの組み立て
2 加速を決めるストレスと故障メカニズム進展の関係
2.1 α型(増加型)のモデル式を活用した加速評価
2.2 β型(最適値型)のモデル式を活用した加速評価
2.3 γ型(減少型)のモデル式を活用した加速評価
3 試験結果はストレスの組み合わせ方や順序で変わる
3.1 加速させるための要素を選ぶ
3.2 加速させるため律速過程を選ぶ
3.2.1 故障メカニズムをフローで描く
3.2.2 律速過程を選ぶ
3.3 多種類同時ストレス
3.4 多種類順次ストレス
3.5 ストレスは全行程を考えること
3.6 熱/湿気/振動ストレスの加える順序は
3.7 複数の要素のある製品の加速試験
3.8 ステップストレス試験
4 わからない故障は市場ストレスを参考に決める
4.1 市場のストレスを把握すると再現できた例
4.2 市場のストレスを無視したため失敗した例
5 故障メカニズムのフローを工夫する加速方法
5.1 小さいストレスをカットするする方法
5.2 ストレングスを弱くする方法
5.3 ある程度劣化させた試料で試験をする方法
5.4 劣化要因を明確にして強化する方法
5.5 試験環境を特化させる方法
5.6 故障判定を厳しいところに設定
5.7 要素による加速
6 湿気加速試験
6.1 金属の腐食
6.2 樹脂と85 ℃85%環境の意味
6.3 樹脂の透湿は蒸気圧法
6.4 85 ℃85%試験のデータが温度試験データによく間違われている例
6.5 湿気加速試験の注意事項まとめ
6.6 線形累積損傷則の湿気ストレスへの応用
6.7 高温高湿試験が加速試験か、耐力試験か、参考試験かの見分け方
7 環境変化とサイクル試験
7.1 高温通電試験
7.2 温度サイクル試験のストレス源には種類がある
7.3 温度サイクル試験と熱容量
7.4 温湿度サイクル試験
7.5 温湿度サイクル試験と熱容量
7.6 頻度を高くする方法の注意点
7.7 低サイクル疲労
あとがき
アイリングモデルが泣いている